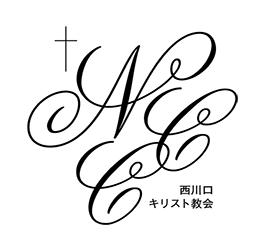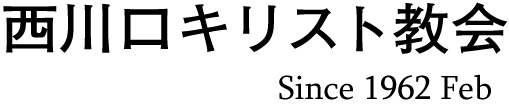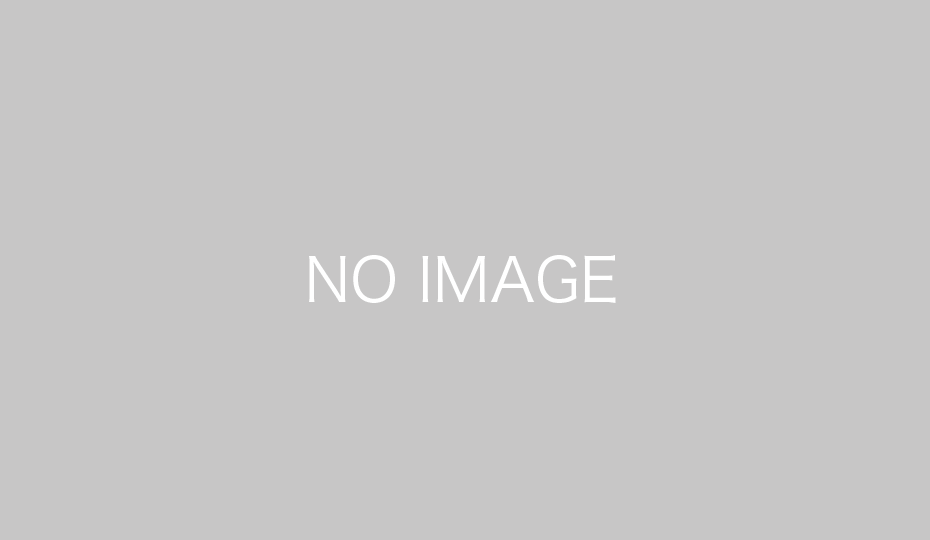「心の貧しい人々は、幸いである、天の国はその人たちのものである。」
マタイによる福音書 5章3節
マタイによる福音書5章3~12節の山上の説教は、イエス様が語られた八つの祝福の言葉(八福)として知られています。この箇所は単なる理想的な教えではなく、戦争、対立、分断があふれる現代社会を生きる私たちに「どう生きるか」「いかにして平和を実現するか」を問いかけています。「平和と癒し」という主題のもと、私たちの日常における具体的な実践について学んでまいります。
第一に、聖書は「謙遜から始まる信仰の道筋」を示しています。「心の貧しい人々は幸いである」とは、自分の限界を認め神に頼ることから信仰が始まることを教えています。現代社会は「自立」と「自己実現」を求めますが、イエス様は別の道を示されました。私たちには世界に完全な平和をもたらす力はありませんが、その限界を認める謙遜さこそが神の力に触れる入口となり、平和への歩みの出発点となるのです。
第二に、聖書は「痛みを通して与えられる慰めの恵み」を教えています。「悲しむ人々は幸いである」という言葉は、現実の苦しみに正面から向き合い、それを神に委ねることの大切さを語っています。世界の理不尽な出来事に心を痛めることは決して無駄ではありません。真の慰めは痛みを無視していては得られず、神から慰められた人こそが他者の痛みに寄り添うことができ、そこに癒しの連鎖が生まれるのです。
第三に、聖書は「柔和と憐れみによる平和の実現」を提示しています。「柔和な人々」「憐れみ深い人々」への祝福は、力や声の大きさではなく、相手を理解し具体的な愛の行動を示すことの重要性を教えています。家庭での感謝と励まし、職場での建設的な協力、地域での理解と支援――これらの小さな実践が平和という大地を耕し、神の平和(シャローム)を地上にもたらす尊い働きとなります。
現代において「平和と癒し」を生きるとは、この世の効率や競争という基準ではなく、イエス・キリストの愛と正義という価値観で現実を判断し、行動を選び取ることです。義に飢え渇き、心の清さを求め、平和を実現する者として、神の子と呼ばれる使命を果たしていきたいのです。
私たちの信仰生活の目標は、日々の選択において意識的に平和と癒しの実践を重ねることです。争いと分断があふれる社会の中で、私たちクリスチャンこそが「平和を実現する人々」として、神の愛と平安を具体的に示していく使命があるのです。マザー・テレサの言葉のように、「小さなことを大きな愛をもって行う」ことから始めて、家庭、職場、地域、教会において神の平和を運ぶ器となりましょう。