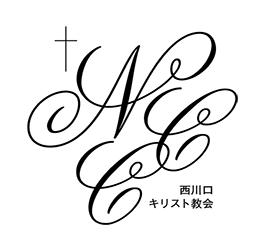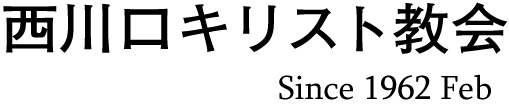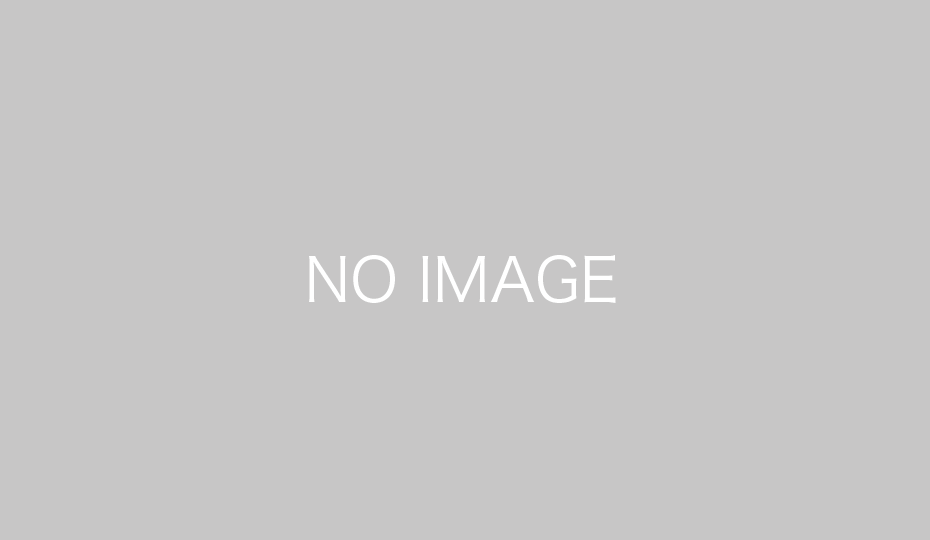2025年4月13日(日)
主日礼拝 宣教要旨
聖書箇所 マタイによる福音書 27章32-44節
「『他人は救ったのに、自分は救えない。イスラエルの王だ。今すぐ十字架から降りるがいい。そうすれば、信じてやろう。』」
マタイによる福音書 27章42節
棕櫚の主日は、イエスがエルサレムに入城された日であり、人々の期待と神の示す現実の隔たりが描かれています。人々は「ホサナ」と歓声を上げ、ダビデの子孫として国を回復する王を期待しましたが、わずか数日後には「十字架につけよ」と叫ぶようになりました。この変化は、人間の心の揺らぎやすさと利己的な本質を映し出しています。
マタイによる福音書27章に描かれる十字架の場面には、人間の弱さや罪深さが凝縮されています。権力者の自己保身、群衆の扇動、親しい人からの裏切りなど、イエスが体験された苦しみは現代社会にも形を変えて現れています。しかし、最も弱く惨めに見えるその場所こそ、神の愛の真の強さが現れる場所なのです。
「神の子なら自分を救ってみろ」という嘲りに対し、イエスは沈黙を守られました。現代社会は即効性と目に見える結果を求めますが、イエスは苦しみから逃げるのではなく、正面から受け止められました。この沈黙は無関心や無力さの表れではなく、人間の苦しみを最後まで共に担い抜く深い愛の表れです。十字架上でイエスは「わが神、なぜわたしをお見捨てになったのですか」と叫ばれました。この叫びは、神との関係が断ち切られたように感じる極限状態から発せられた魂の底からの叫びですが、同時に神の愛の究極的な表現でもあります。イエスは人間が最も神から見放されたと感じる場所に、自ら降り立ってくださいました。
イエスの死の瞬間、神殿の垂れ幕が上から下まで裂けたことは、神と人との間にあった障壁が取り除かれたことを示しています。神への道はすべての人に等しく開かれ、学歴や社会的地位、過去の過ちさえも、神に近づく資格を左右することはありません。十字架の愛に応える実践として、苦しむ人のそばに静かに寄り添うこと、声を上げづらい人の思いに耳を傾けること、分断の中で橋渡しをすること、自分の弱さを受け入れること、見返りを求めず愛し続けることが挙げられます。これらは特別な行為ではなく、日常の小さな場面こそが愛を生きる機会なのです。
棕櫚の主日から始まる受難週は、イエスの苦しみと愛の意味を心に刻む時です。イエスが十字架で示された神の愛―見捨てられた人のそばに立ち、声にならない痛みに耳を傾け、分断の中で和解を求め、弱さをもって他者とつながること―に、私たちも小さな歩みで応えていく者とされますように。この受難週、イエスの足跡を心に刻みつつ、主の愛に応える歩みをともに始めてまいりましょう。