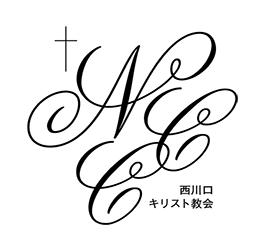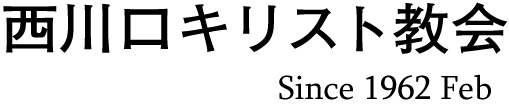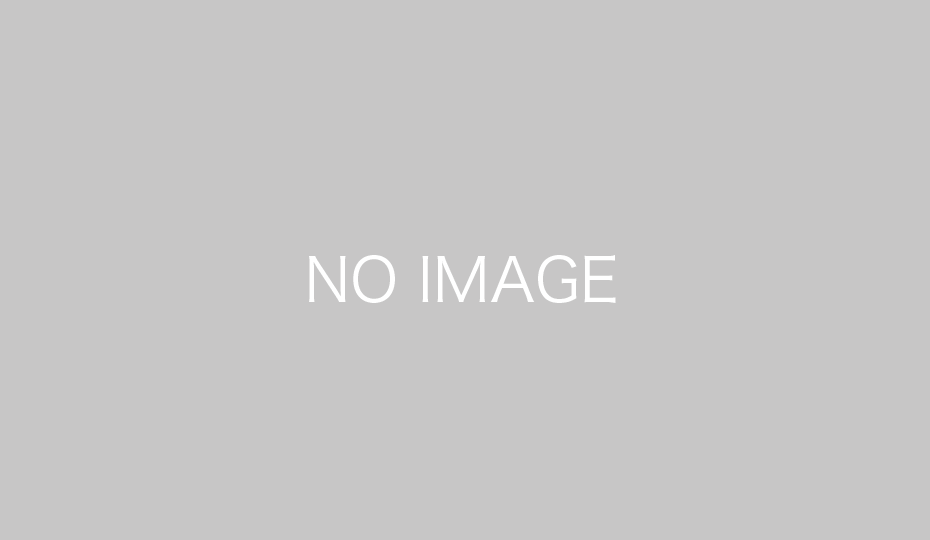パウロは「わたしは自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている」(ローマ7:19)と嘆いた。「善をなそうと思う自分には、いつも悪がつきまとっている」(ローマ7:21)、つまり「自分は惨めな罪人である」という認識の告白である。これは「信仰者パウロ」の告白であった。復活の主イエスに出会う前は「神の前に落ち度がない」と誇っていたパウロは、主イエスを信じ、神の御心に従おうとする中で「なお従い得ていない自分の罪」を告白するようになった。
ダビデの真剣な祈りもまた、彼の敬虔な信仰をあらわしている。ダビデは「この罪深い出来事を隠蔽してしまおう」と思ったかも知れないし、また実際にそうすることのできる立場にあった。しかし預言者ナタンを通してその罪を指摘され、このように祈っている。まことに鋭い「罪」の感覚である。神の前に信じ従うべき自分が神を裏切った。それならば「神から逃れてしまえばいい」という道もある。しかしダビデはそうしなかった。ダビデにとっては神こそ「依り頼むべき方、従うべき方」であり、「神なしに自分の人生は全うできない」という思いがあったからである。日本では「教会に行くと≪罪、罪≫と言われるからイヤだ」という人がよくいるという。確かに「神に生命を頂いている」と信じる人ほど罪意識も重いのかも知れない。主イエスは「悔い改めよ」というメッセージを語られた。「悔い改め」の第一歩は「罪の明確な意識」、すなわち「離れようとしても常に罪が自らの前にある」という認識である。
ダビデは「あなたに、あなたのみにわたしは罪を犯し 御目に悪事と見られることをしました」(6節)と告白する。ここで言われている「罪」とは、部下ウリヤに対する罪のはずである。ダビデはウリヤの死を願い、故意に戦場の最前線に立たせて死なせたのであるから。しかしダビデは神に向かって「あなたのみに罪を犯した」と言う。赦しは神の憐れみによってしか頂くことができないので、ダビデはこのように告白せざるを得なかったのである。我々の犯す誰に対するどのような罪も、それらはすべて「神に対する罪」である。悔い改めることなく罪を罪のまま覆い隠し放置している限り、「神との関係」は壊れたままである。「罪」とは「神との関係を自ら壊すこと」に他ならない。
「あなたの言われることは正しく あなたの裁きに誤りはありません」(6節)とダビデは認める。「神の裁きの正しさ、厳しさ」を前にして、罪を犯す人間の側から言い逃れをすることは不可能である。そしてそのことを認めるところでこそ、「罪を赦す神の恵み」にあずかることができる。
「わたしは咎のうちに産み落とされ 母がわたしを身ごもったときも わたしは罪のうちにあったのです」(7節)とダビデは述懐する。人間が持つ「神の意志に反する罪」は生まれながらのものである。それは既に身体に染み込んでおり、自分で努力して洗い落とすことのできるものではない。「秘術」(8節)とはひとつの「礼拝の行為」である(参照:レビ1章「燔祭」)が、そのような行為によって罪が赦されるわけではない。神はそれを望まれないのである。むしろ神は「自分は神の前に罪深い存在なのだ」と認識する「知恵」(8節)を我々に授けられる。「自分の罪を知り告白すること」が悔い改めの第一歩である。
「ヒソプの枝でわたしの罪を払ってください わたしが清くなるように。わたしを洗ってください 雪よりも白くなるように」(9節)とダビデは祈る。「あくまでも罪を払いのけることのできる方は神以外におられない」という告白である。「喜び祝う声を聞かせてください あなたによって砕かれたこの骨が喜び躍るように」(10節)とあるが、「骨」とは「人間の中心的な部分」を指す言葉である。ここには「人間の最も大事な部分が罪によって破壊されている」というダビデの深い洞察がある。そのような状態である限り、人間はまことに神を喜ぶことはできないのである。
それゆえにダビデは「神よ、わたしの内に清い心を創造し 新しく確かな霊を授けてください」(12節)と祈り求める。 「心」とはここで「霊」と同義である。人間はそもそも「神と対話する」「み言葉を聞き分ける」ような「霊」を創造して頂いている。しかしそのように神と正しい交わりを持つ「霊」が「罪」によって破壊されているので、「新しく」もう一度授けてほしいとダビデは願うのである。この切なる願いは「人間が自分の努力では善をなしえない」という認識に裏打ちされている。神の霊と我々の霊が響き合うところに、神と我々とのまことの関係が成り立つ。「神と対話し神の御心を聴き分ける霊をもう一度創造してほしい」「神の霊が注がれるように」「神からの働きかけが豊かに与えられるように」とダビデは真剣に神に求めた。
重ねてダビデは「御救いの喜びを再びわたしに味わわせ 自由の霊によって支えてください」(14節)と願う。人間は罪赦されて初めてまことに神を喜ぶことができる。「自由」とは「自分から進んで行う霊」であり、それも自らの努力によって獲得できるものではなく神から頂くものである。新約の時代に生きる我々は、主イエスによって神の憐れみを知ることができた。我々は主イエスに出会い、神の前に罪人であることを知り、それゆえにこそなお赦し憐れみ生かそうとする神のゆえに生かされることを知った。だから、キリスト者は神を「信じ」神に「従う」者とされる。信仰とは「ゆるされた、ありがたや」で終わるものではない。信仰者には「神の恵みをおぼえ悔い改め従っていく生活」「恵みに応えて生きていこうという応答の生き方」が求められているのである。神に従うことの中で、我々はまた自らの罪を知らされる。我々は決して「只一度だけ」悔い改めれば良いのではない。「キリスト者の生活は日々悔い改めである」(ルター)。救いは完了形のものではなく常に求めていくものであり、そうしていくのがキリスト者の生活である。「神は、わたしたちが行った義の業によってではなく、御自分の憐れみによって、わたしたちを救ってくださいました。この救いは、聖霊によって新しく生まれさせ、新たに造りかえる洗いを通して実現したのです」(テトス3:6)。