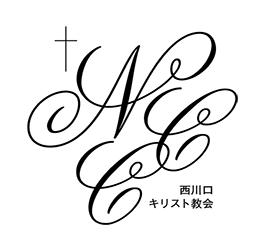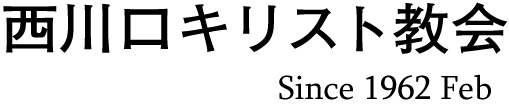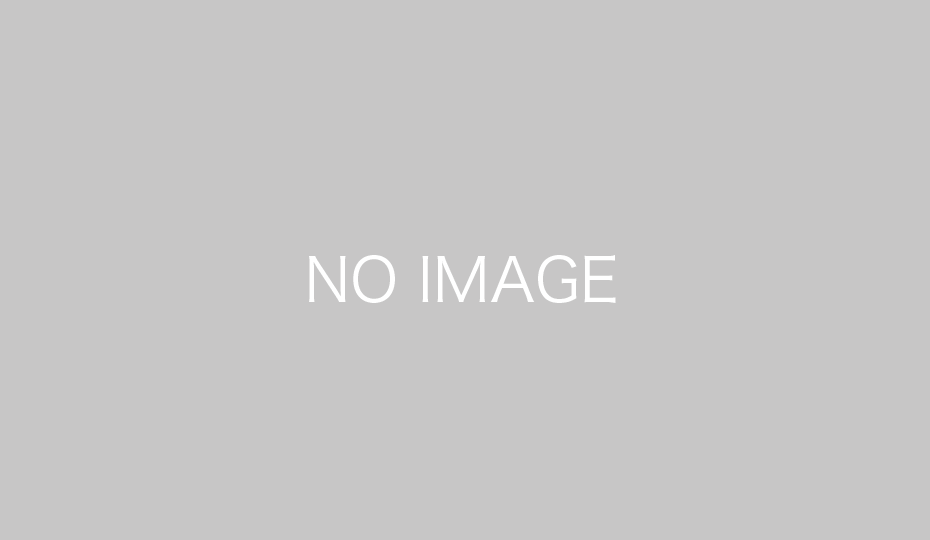主イエスにとって「十字架の死」は、「自分の信じた信仰に殉ずる」ということに留まるものではなかった。「過ぎ去らせてください」と主イエスが祈られた「杯」(26:39)とは、ご自身が受けなければならない「十字架の死」である。それは多くの人々の「罪の赦し」のための「死」である。それは本来、神の栄光をあらわすべきであるにもかかわらず神に背を向け、神に対して罪を犯している人間ひとりひとりが背負わなければならない、「罪の裁き」としての「死」である。主イエスは、罪人に代わってその「罪の裁き」としての「死」を受け入れることによって、「神の赦し」をとりなして下さった。そういうわけで、主イエスの十字架の「死」は、単なる 「信仰に殉ずる死」とは同一視できないのである。
「神の裁き」としての「死」を受けるのはどんなに厳しいことか、本当にご存じであったのは主イエスだけであった。それゆえに、主イエスはこのように祈られたのである。「父よ、できることなら、この杯をわたしから過ぎ去らせてください」という祈りに続け、すぐさま「しかし、わたしの願いどおりではなく、御心のままに」(26:39)と祈られたかどうかは不明である。弟子たちも寝たり起きたりしながら、その祈りを聞いていたに違いない。もしかしたら、「もし他の方法があるならば・・・」という祈りが長い時間繰り返されていたかも知れない。
主イエスが祈りの合間に弟子たちのところへ戻られると、彼らは眠っていた。そこで主イエスは「誘惑に陥らぬよう、目を覚まして祈っていなさい」(26:41)と語りかけられた。ここで主イエスは、ついつい眠ってしまう弟子たちを責めているのではない。「主イエスと共に生き、共にその苦しみに預かりたい」という気持ちがあっても、なかなか体がついてこないことを、主イエスは人間のからだを持たれたからこそ知っておられた(参照:ヘブル2:14−18、4:14−16、5:7)。その「誘惑」を乗り越えるには、上からの力を頂くより他にない。それゆえ主イエスは「祈りなさい」と弟子たちに勧め、自らもそのように繰り返し祈られた。主イエスご自身も、祈りなくしては神の御心に生きることができなかったのである。
やがて主イエスは「時が近づいた」(26:45)と宣言された。聖書には「時」を表わす二つの言葉がある。一つは「クロノス」であり、平易に言うならば「時計の刻む時間」を表わす言葉である。もう一つは「カイロス」であり、これは時間上のある「点」としての「神の時」を示す言葉である。主イエスはご自身が十字架の苦しみを受ける「時」もまた、「カイロス」、備えられた「神の時」であるとして捉えられた。そしてご自身が受ける苦難を「神の時」の出来事として受け入れるために祈られたのである。
我々もまた、人生において様々な苦しみを受ける。それを「神の時」の出来事として受けることは簡単ではない。しかしそのようにできるように祈り続けることを、我々は求められている。それは、神の御心が成就する「神の時」を待つ祈りである。苦しみや課題を背負わされる「時」も、偶然ではなく「神の時」であるから、我々は神が御心を成就される「神の時」を祈りつつ待つのである。次週分の『聖書教育』に紹介された左近淑氏の言葉を紹介したい。「ところが聖書宗教は、神々を人間が利用するということは、ゆるさない。神は人間の自由にならない。だから神が働いて下さるのを待つ。どんな絶体絶命の時でも、自分ではどうにも見込みがない、どうにもならないところで、<なお>神を信頼し抜く。だから、古代宗教の呪文や呪術が位置を占めるところに、神の奇跡に対する信頼が位置を占める。・・・聖書とキリスト教は最後まで与えられた人生をあきらめない。<時>は必ず変わる。<時>は神によって必ず変えられる。神の徹夜のゆえに、神の血みどろの闘いの故に変わる。それを認めるのが、キリスト教です」(左近淑「救いを見なさい 出14:10−14」、『日本の説教Ⅱ 14』31頁、日本キリスト教団出版局、2007年)。