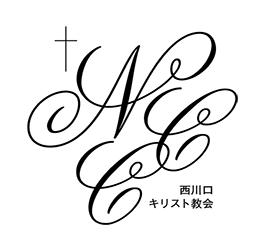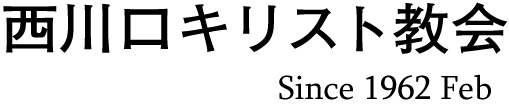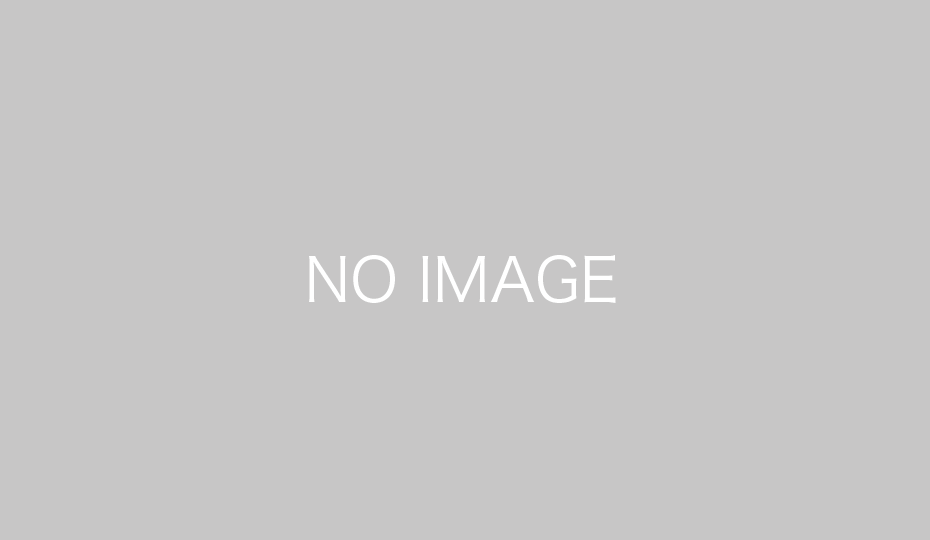「主よ、主よ、わたしたちは御名によって預言し、御名によって悪霊を追い出し、御名によって奇跡をいろいろ行ったではありませんか」(7:22)とは、主イエスに対して「自分はこんなにいろいろなことを行ったよ」と、「わざ」を主張する人たちの姿である。「しかしそれが救いの条件なのであろうか、きっぱりとこう言おう」と主の言葉は続く。「あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども、わたしから離れ去れ」(7:23)。「知る」とは聖書の中で特別な言葉である。すなわち「頭で知的に知る」のではなく「人格的な交わりをもつこと」を示す言葉なのである。ここでは「主イエスとの交わりに生きたかどうか」が問われている。「不法を働く」(7:23)とは文字通り「神の律法、戒めを守らない」ことである。主イエスは繰り返し、「あなたがたはこのように聞いているが、しかしわたしはこう言っておく」と言われる。主イエスは、たとえ「殺すな」という律法は守っていても、他者を蔑んだり貶めたりすることがあるならば、その人は既に神の律法を犯していることになるということを明らかにされた。「律法を守る」とは「字面を守る」ことではなく、「神の意志がどこにあるのか求めて生きる」ことなのである。
神の意志は「神を神とし、神に依り頼む」「神に与えられた生を誠実に生きる」「人を愛し大事にしていく」ところにある。主イエスは律法を廃止するためではなく成就するためにこの世に来られた。「律法を蔑ろにしている」というご自身への批判に対して、主イエスは一番大事なことが「神との交わり」「神を愛し、そのところから生きていく」ことだということを示された。神と我々との「関係」が問われていくのである。
24-26節の「家と土台」のたとえは、当時この話を聞いていた人々にとっては大変リアルな情景を思い起こさせるものであった。パレスチナにおいては乾季と雨季との間に激しい差がある。雨季に入ると集中豪雨が起こり、川がなかったようなところにも水が溢れ出し、いろいろなものを飲み尽くしていく。一方で乾季になれば水が引き、地面には水の通った跡が残る。このたとえは、「終わりの日に来たるべき神の審判」を示している。主イエスが「山上の教え」で語っておられるのは、「終末倫理」である。終わりの日、神の裁きの前に我々は「神の意志を行っているかどうか」と厳しい問われかたをする。それは決して「義とされるためのわざ」を求められているのではない。「神といかに向き合って交わりの中に生きているか」「神の言葉にどれだけ本気で聞き従って生きていこうとしているのか」と、生き方そのものが問題にされるのである。「自分はもう神を愛し、自分を愛しているように他者をも愛している、こんな良いことをしている」と神の前に主張する生き方ではなく、神と常に向き合って格闘する生き方が求められている。その格闘の中で、我々は祈らされていくからである。それが「主イエスを知る経験」である。「山上の教え」は「信仰への招き」である。「神の顧みの中に絶対的な信頼を置け、与えられた生を喜び、そこで受けたものを神からの賜物として受け取れ、そして神に喜ばれる生き方をせよ」と、我々は招かれている。父なる神への信頼に生き、一人ひとりの生に神が関わって下さるのだということを受け止め、「どうせできない」と諦めるのではなく神の戒めを受け止めながら生きていくことが求められている。終わりの日になされるのは業績の評価ではない。「神との交わり、神との関係に生きたかどうか」というところに目が注がれるのである。
「イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく、権威ある者としてお教えになったからである」(7:28-29)。「律法学者」は律法を学び解説する人である。しかも、単純に学問として解説するだけではなく、宗教的な戒めを解説し生活に適用させ、指針を与えていた。そのような意味で彼らは社会の中で尊敬される存在であった。しかし、主イエスはそのようにではなく「権威ある者として」ご自身を示された。ここでも、どのように主イエスに向き合うのか、どのように主イエスを告白していくのかが大切に問われている。