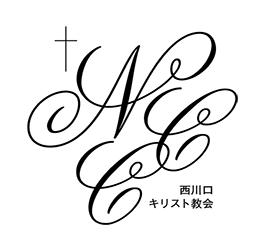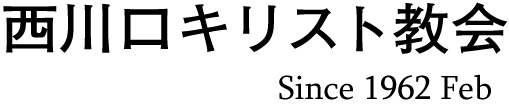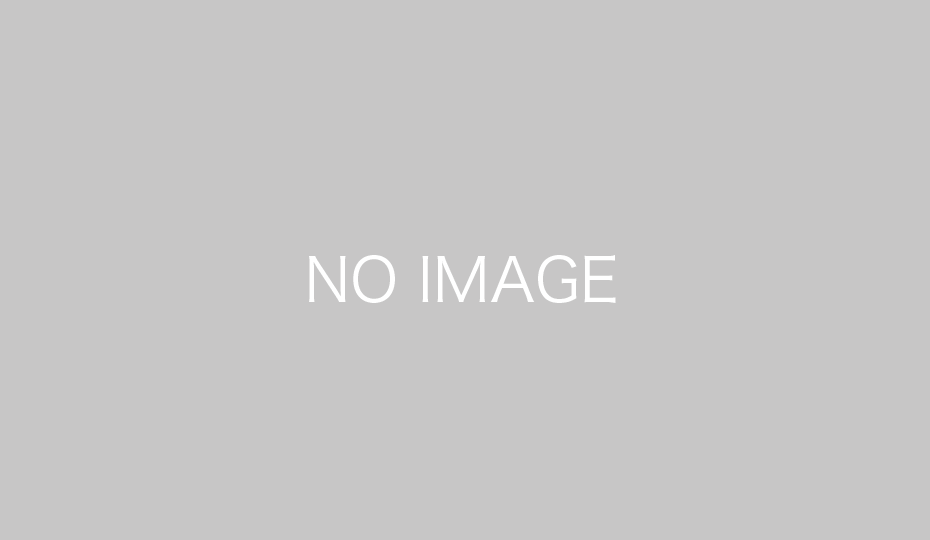イスラエルの民はギルガルのあたりからエリコへ、つまり東から西へ、そしてヨルダン川と地中海の間の山地へ入って行った。地中海のあたりには海から移り住んできたヘテ人、ヒッタイト人の強力な都市国家が存在していた。それゆえイスラエルの民はそのような都市国家の影響の及ばない山地へ入り定住したのである。彼らはもともと小家畜を牧畜する遊牧民であった。そのようにしてエジプトからカナンへの旅の生活の資を得ていたわけである。山地に定住してからは農耕も営むようになり、小家畜飼育と兼業の形をとっていた。また、そのような山地をすべて平定していったわけでもない。あのエルサレムでさえも、イスラエルのものになったのはダビデの時代である。無論、土地を広げていく中での小競り合いはあったであろうが、「どんどん入ってそこに住む人々を皆殺しにした」というのは実状ではない。そこで得た土地は「神様から頂いた」という信仰が、旧約聖書に表現されている。「その土地は神のものだ、自分たちのものではない」という信仰の表現が「皆殺し(聖絶)」なのである。
イスラエルの民は農耕をひとつの生業としたので、収穫の時期になると、ベドウィンなど本物の遊牧民が侵入してくる。その時にイスラエルの民は改めて戦わなければならなかった。職業軍人はいないので農民たちが結集して防御する。その時のリーダーが「士師」と呼ばれた。「士師」は「皆で話し合って選び出した」とか「組織を整えた上でそこにリーダーとして立てた」人であるというよりも、むしろ「神の霊に促されてリーダーシップをとった」人物である。「士師」は戦争が終わると普通の農民に戻った。そして次の戦争の際には次のリーダーが登場する。
カナンに定着したイスラエルの民は、こういう意味においても民主的な性格の強い共同体を形成した。王が権力を持って統治していく共同体ではなかったのである。それはまた同時に「契約共同体」、すなわち「神との契約」に堅く立つ共同体であった。「神が我々の主だ」「神が主権を持つのだ」という信仰に立つ共同体であった。何よりもイスラエルの民はエジプトでの隷属状態のなかで苦しんだ記憶を持つ。そしてそこから解放されたことを常に想起していた。自分たちはエジプトの王制のような権力構造を持たず、互いに責任と義務を負いあう共同体を形成したいと願ったイスラエルの民は、部族ごとにそのような共同体を形成した。その中で神の意志を民に伝え想起させる役割は「士師」が担った。「士師」は人々を戒め、「神こそ主である」ことを語った。戦いにおいても「これは主の戦いなのだ」ということを常に人々に示し、神を中心とし主権者とする信仰を導いていった。 このようにイスラエルの民は神の前で人々が平等であり民主的に事柄を進めていく共同体を形成したので、「士師」は国家元首としての意味合いは持たない。同時に「士師」は神の言葉を人々に語る「預言者」という役割も担っていたと言える。ルツ1:1「士師が世を治めていたころ」という冒頭の表現には、このような背景がある。
さて、その頃「飢饉が国を襲ったので、ある人が妻と二人の息子を連れて、ユダのベツレヘムからモアブの野に移り住んだ」(1:1)。「モアブ」はイスラエルの民の定住地とは違う所であったが、飢饉という状況のゆえに彼らはモアブに移住しなければならなかった。山地での農耕は厳しい条件の中にある。ひとたび不作になれば、外地に移住せざるを得ない人々もいたのである。
「ある人」、すなわちエリメレクは妻ナオミと二人の息子を遺して亡くなった(1:3)。二人の息子はモアブ人の女性を妻とし、10年ほど共にモアブで暮らしたが、彼らも相次いで亡くなった(1:4−5)。このような状況の中で、ナオミは故郷であるユダに帰る決心をする。その時、一緒に遺された二人の嫁、オルパとルツも、ナオミに従ってユダへ移住しようと願った(1:6−7)。
しかし、ナオミは二人の嫁を思いとどまらせようと説得する。12節以下のナオミの言葉の背景には、「自分の家系を絶やさないために、夫が死ぬとその妻は夫の兄弟に嫁ぐ」という当時の法律がある。しかし、ナオミにおいてはもはや新しい息子を産み、嫁たちと結婚させるという可能性はない、ということである。
ナオミの悲痛な言葉は続く。「・・・あなたたちよりもわたしの方がはるかにつらいのです。主の御手がわたしに下されたのですから」(1:13)。イスラエルの信仰は「苦しい目に遭わせる神は信じない」ではなく「神は試練をも与える」というものである。「ルツ記」においては、この信仰に堅く立つナオミももうひとりの主人公である。夫に先立たれた女性はいつの時代にも厳しい状況に置かれる。この先どういう具合に生きていくのか先の見えない不安定さの中で、遊女のようになる人も多かった。ナオミは二人の嫁の行く先を案じ、彼女たちはモアブの人間なのだから自分の故郷に留まり、新しい嫁ぎ先を見つけるよう勧めたのである。
オルパはナオミとの別離を悲しみつつ、ナオミの言葉にしたがって去っていったが、「ルツはすがりついて離れなかった」(1:14)。そして言う、「あなたの民はわたしの民、あなたの神はわたしの神」(1:16)。これは故国モアブを離れてなおナオミに仕えていくルツの決意の言葉である。
さて、ルツはナオミと一緒にユダノベツレヘムへ帰り、そこでボアズに出会う。ボアズはエリメレクの親族であったが、裕福な資産家になっていた。ルツは、このボアズの厚意を受けるようになる。ミレーの絵で有名な「落ち穂拾い」の場面がここに登場する。この慣習については聖書の様々な箇所で語られているが(レビ19:9など)、「貧しい人のために、収穫の時に全部刈り取らないで残しておく」という取り決めがそこにはあった。特別な計らいにより、ルツはボアズの農地で落ち穂拾いをさせてもらえることになったのである。
ナオミは、エリメレクの親戚であるこのボアズを、「あなた(ルツ)が幸せになる落ち着き先」(3:1)と見定め、計らう。当時の「結婚」は単なる恋愛感情の結果ではなく、「家系を守る」という側面を強く持っていた。ある土地の継承者が亡くなった際、「誰がその土地を引き継ぐか」という問題が発声するが、そこには優先順位があった。ナオミとルツの事例においては、ナオミに遺された土地を買い取る権利に関してボアズよりも優先権の高い人物が存在した。
そこでボアズは十人の長老を証人として同席させ、「モアブの野から帰ってきたナオミが、わたしたちの一族エリメレクの所有する畑地を手放そうとしています。それでわたしの考えをお耳に入れたいと思ったのです。もしあなたに責任を果たすおつもりがあるのでしたら、この裁きの座にいる人々と民の長老たちの前で買い取ってください。もし責任を果たせないのでしたら、わたしにそう言ってください。それならわたしが考えます。責任を負っている人はあなたのほかになく、わたしはその次の者ですから」(4:3−4)と提案する。
この「責任を果たす」という語は、口語訳聖書では「あがなう」と訳されていたが「買い取る」という意味である。イスラエルの人々にとって、神から与えられた土地を部族で守っていくことは大きな責任であった。そして直接の継承者がいないときはそれを受け継いでまもっていく責任者として一番近い近親から順にその権利責任を持っていくという決まりになっていたのである。エリメレクの子は既にいない。エリメレクの次男の妻ルツに子が生まれたら、その子がその正統な継承者になるという意味があるので、この場面で「土地を引き継ぐ」ということは、「ルツと結婚する」ということも付随してくる問題になっているのである。
この提案に対し、最優先の権利を持つ親戚は「そこまでの責任は負えない」と、その権利を放棄し、ボアズがエリメレクの土地をナオミから買い取り、同時にエリメレクの次男の妻ルツを妻に迎えることで「故人の名をその嗣業の土地に再興するため、また故人の名が一族や郷里の門から絶えてしまわないため」の役割を引き受けた。そしてボアズとルツの間にはオベドが生まれる。「オベドはエッサイの父、エッサイはダビデの父である」(4:17)。更に「マタイによる福音書」の冒頭の系図を見ると、その先に「メシアと呼ばれるイエスがお生まれになった」(マタイ1:17)。
「ルツ記」というこのひとつの書物の言わんとしていることは、「神から選ばれたイスラエルの民」とは「単なる血縁共同体ではない」ということである。外国の女であるルツも、神の救いの歴史の中にこのようにして組み入れられていった。神は「イスラエルそのもの」のみではなく「万民」を祝福するために、まずイスラエルを選ばれたた。それは「血縁」よりも「信仰」の共同体である。それゆえに神はそこからご自身のわざをなしていかれた。そのような意味において、旧約聖書は新約聖書の預言、イエス・キリストのわざを目指している歴史の書であると言える。