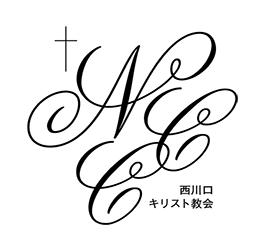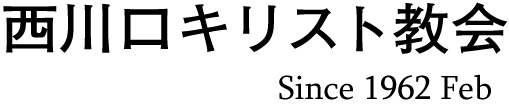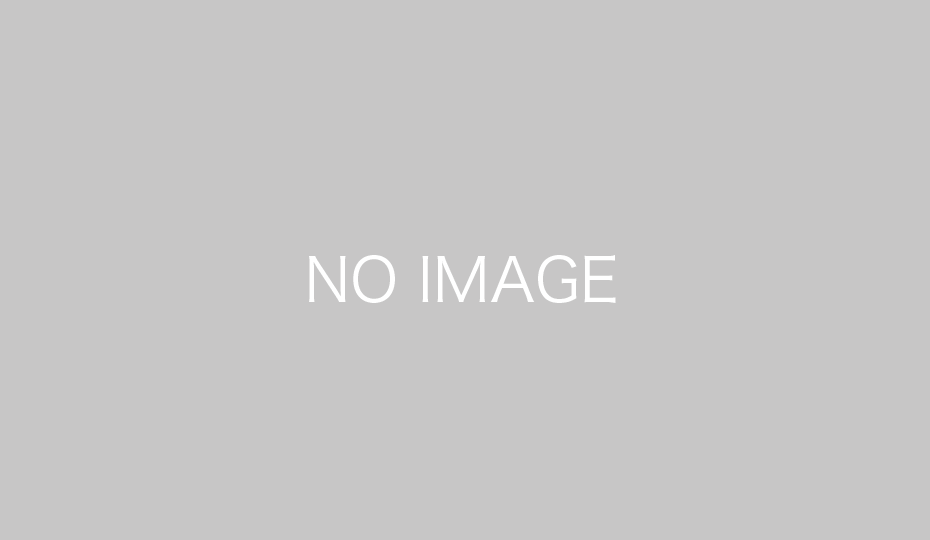キリスト者は「神の霊によって礼拝」(3:3)するものであることをパウロは強調する。律法に強制されて礼拝を行うのではなく、神の霊の導きにより礼拝をささげるということである。そして、「イエス・キリストを誇りとし、肉に頼らない」(3:3)のがキリスト者であると続ける。「誇り」は人間を生かす原動力として重要なものである。しかし、人間がキリストではなく、この世において頼ろうとするものを「誇り」とするとき、そこには「他者との比較」が生じ、互いの関係の破壊が生じるのである。
パウロ自身は、「誇り」とするものを数多く有していた。パウロは「生まれて八日目に割礼を受け」た生粋のユダヤ人、しかもダビデ王と同様に「ベニヤミン族の出身」であった(3:5)。更に、碩学ガマリエルの門下で律法を学んだ経歴を持ち、「熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非のうちどころのない者」(3:6)としてパウロは大きな「誇り」を持って生きてきたと越し方を振り返る。しかし、「わたしにとって有利であったこれらのことを、キリストのゆえに損失とみなすようになったのです」(3:7)。それは、パウロが「キリストを知ることのあまりのすばらしさ」(3:8)に圧倒されたゆえであった。「知る」という言葉の意味には解説が必要である。ギリシャ的な意味での「知る」とは、「認識する」ことである。認識される対象があり、認識する自己がある。両者は明確に分割されており、認識の主体である自己は、「認識した」ものの中から自分に役立つ部分を利用する。一方、ヘブライ的な意味での「知る」とは、「人格的な交わり」の意味合いを強くする。「キリストを知る」とは「キリストと交わる」ことである。自分の外側に認識の対象としてのキリストがおられるのではなく、自分がキリストの内におり、交わりを頂くのであり、その喜びに立ち続けよ、とパウロは勧めるのである。その時、今まで「自分はこれがなければだめだ」とこだわり誇りに思っていたこの世のものが、実は自分を鼻持ちならない、腐臭を放つものとさせるものなのだということに気づかされる。
「キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義」(3:9)とは、自分の義、すなわち自分の正しさではない。それは神が生み出して下さる「正しい関係」である。キリスト者は、キリストの復活によって罪贖われ「義」とされた存在である。そのキリストは、今もなお生きて、人を神との正しい関係に導き、神にあって生かすために働いておられる。
パウロにとって、キリストの復活にあずかることは、キリストの「苦しみ」(3:10)にあずかることであった。信仰があるゆえの苦しみも頂くが、それによってこそ、キリストの復活にもあずかるという理解である。それはまたパウロにとっては「伝道者としての苦しみ」を受け止めていくことでもあった。
キリストと我々の関係は、「既に」成った面と「未だ」完成しない面を併せ持つ。パウロはそのことを「何とかして死者の中からの復活に達したい」(3:11)と、動的な表現で語る。キリストと我々の関係、信仰生活は、今でもなお現在進行形である。