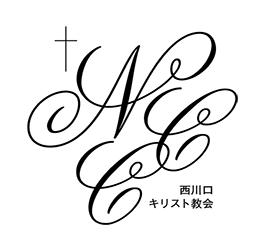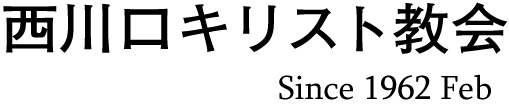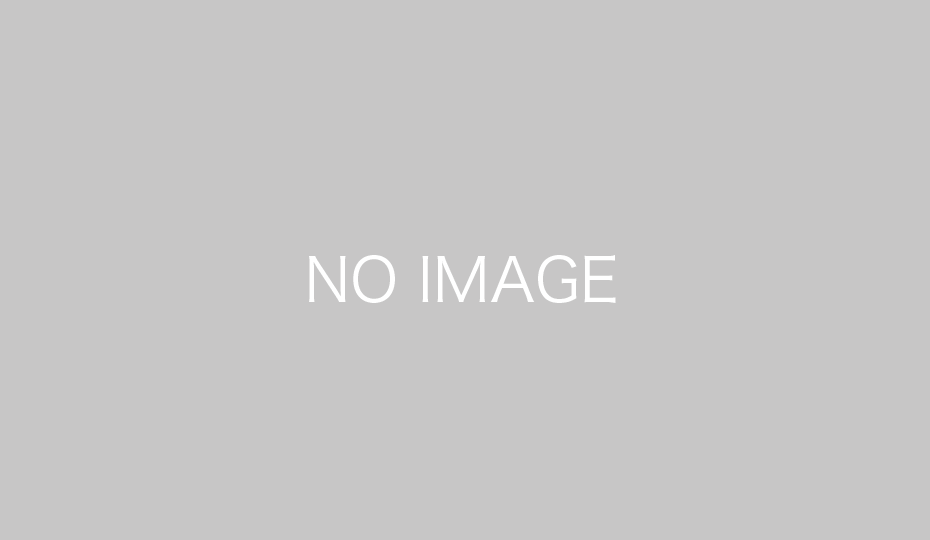2025年2月23日(日)
主日礼拝 宣教要旨(きたかん相互訪問日)
聖書箇所 創世記30章25-30節
「ラケルがヨセフを産んだころ、ヤコブはラバンに言った。『わたしを独り立ちさせて、生まれ故郷へ帰らせてください。」
創世記 30章25節
北関東地方連合で、また連盟で、共に協力伝道のために、祈り協働する西川口教会のみなさまとご一緒に礼拝できますことを、大変うれしく思っております。
きょうのテーマは、父と子が象徴する家族観の中に、無意識に含まれる構造的問題です。在日外国人の友らの人権を侵すこの社会の問題の視座を借りるとき、そこにはまさに「父と子」のいびつな関係というテーマにぶつかります。
吉田舞さんという研究者が、『恩顧と従属的包摂—外国人技能実習制度における労務管理―』という論文の中で、父と子が象徴する疑似家族の持つ問題性を次の通り指摘しています(『技能実習生は、必ずしも直接的な強制や、非人間的な抑圧だけで、管理されているわけではない。むしろ、その制度的立場ゆえに、「よくしてくれている」雇用主に対して、「ものが言えない」状況が強化されることもある』)。そこできょうは、技能実習生の視座を借りながら聖書が語るラバンとヤコブの物語を読み直してみたいのです。
物語の主人公ヤコブは、故郷での行動からいのちを狙われ、母の兄、叔父さんのラバンのところに身を寄せました。ヤコブに会った時、叔父は「29:14 お前は、本当にわたしの骨肉の者だ」と家族的に迎え入れ、ひと月ほど過ぎると「29:15 お前は身内の者だからといって、ただで働くことはない。どんな報酬が欲しいか言ってみなさい」と疑似家族的な雇用関係を結びました。両者のこのいびつな関係は、時間の経過と共にさらに濃くなっていきました。
ヤコブは、そのような中で、きょうの25節でラバンに対して故郷に帰りたいと訴えます(「25 わたしを独り立ちさせて、生まれ故郷へ帰らせてください」)。しかし、ラバンは「27 もし、お前さえ良ければ、もっといてほしい」、「28 お前の望む報酬をはっきり言いなさい。必ず支払うから」と、その声を聞こうとはしませんでした。
教会はこのような父と子的な関係のいびつさ、疑似家族の問題性をみことばを通して越えていくことが期待されているのかもしれません。聖書の神は、神からすれば身勝手にも思われるようなわたしたちの自由をもご自身の事柄として引き受けた神ではないでしょうか。また神はイエスの十字架によって、わたしたちに恩を売り、要望を満たすような仕方でつなぎとめるような在り方を断念なさったのではなかったのでしょうか。わたしたちは、イエスによってあらわされた神を「わたしのお父さん(お母さん)」と告白します。また、イエスの姿から子としての姿を学ぶ者として、すべての人を尊び、互いの関係性を取り戻しながら、まことの自由の中で、いっしょに喜び合いましょう。