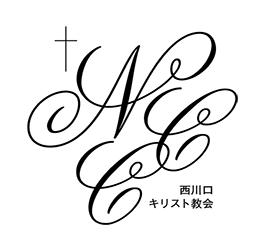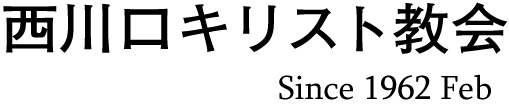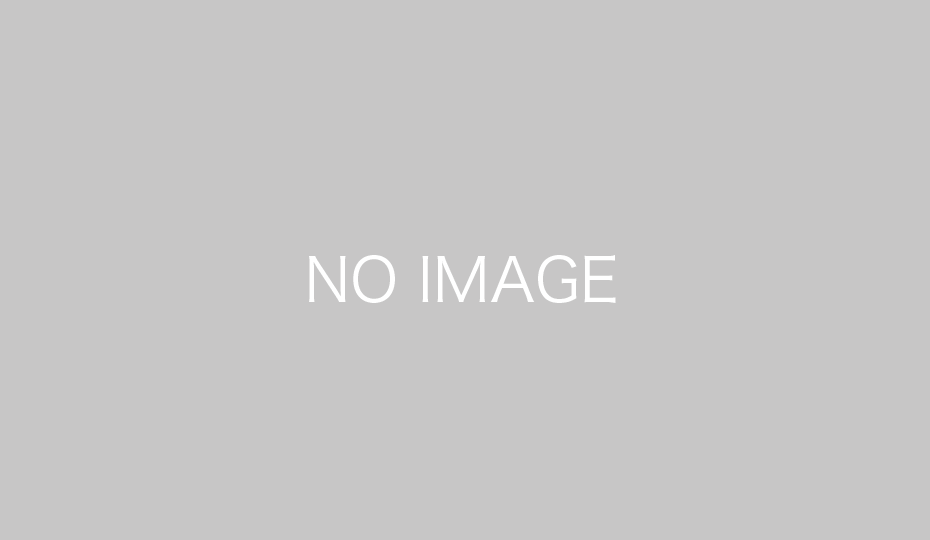詩は「全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ」(1節)という促しによって始まる。「全地に対する礼拝への招き」である。「全地よ」とは二つの事柄を指し示す言葉である。まず、この言葉は「礼拝に集う会衆は、全世界にいる神をあがめる全ての者たちと結ばれている」ことを我々に想起させつつ「さあ、共に主を礼拝しよう」と促す。「主の日」には、ここにいる我々の群れのみならず、全世界に散らされた主にある民がそれぞれに集って礼拝している。世界中には大きな教会も小さな教会もある。そして教会ごとの特色はそれぞれである。しかし「主の日」にはそれぞれの仕方で、同じ主を賛美するために集っている。我々は「主の日」ごとに「全世界に散らされた主の民との、主にある一体感」を覚えながら礼拝するようにされているのである。
「全地よ」という呼びかけのもう一つの意味は、「この礼拝は全世界の民に開かれているのだ、この礼拝に全世界の民が招かれているのだ」ということである。この礼拝は「我々だけの」「我々のためだけの」礼拝ではない。この礼拝の場所に多くの人々が招かれているという思いを忘れてはならない。
我々は引き続き促される。「喜び祝い、主に仕え 喜び歌って御前に進み出よ」(2節)。「主に仕える」とは「礼拝する」という意味でもある。英語では「礼拝」を「サービス(service)」と表現することがある。「礼拝」は「神に仕えること」であり、「一番の神奉仕」とも言える。もちろんキリスト者にとっては、日曜の礼拝の時間帯だけが「礼拝」なのではない。その全生活が「神に仕えること」であり「礼拝」である。そのような意味も込めて、「礼拝」は「最大の神奉仕」であり、神が最も喜んでくださることである。我々は神の栄光に仕え、「神ご自身のみわざが豊かにあらわされるように」という祈りをもって礼拝をささげなければならない。そのような思いがなければ、我々のささげる礼拝は「自分が楽しみたい」がための礼拝、「自分が素晴らしい音楽を聴きたい」がための礼拝になってしまうのである。
「御前」(2節)とは、原語では「顔」を表わす。すなわち「御前に進み出る」とは、「神の顔を見る」「神に会う」ということである。それは具体的にどのようなことなのであろうか。我々は具体的な神の姿形を目にすることはできない。しかし、もう一度主イエスを仰ぎ、主イエスを通して神に出会うことができる。神の前に進み出て、神と向き合い、神の言葉に聞き従うことが、我々のささげる「礼拝」である。
これらの事柄は聖書の示す「神に造られた人間」という人間観に関わりがある。人間は神に造られ生かされている存在であり、神に依拠し神に向き合う者として造られている。「神の似姿」という言葉で人間の本質を表現することがある。人間は神によって「息」を吹き入れられ、「永遠を想う心」を授けられた。
そして人間は「他者との関係」に生き、「他者の言葉に自由に応答する」存在として造られた。それが「人格」の本質であり、人間が人間たる所以である。これが、聖書を通して我々が知らされる「人間」理解である。今日の社会においては、進化論的な発想で「人間は生物の一つに過ぎない」と了解されている。もちろん生物学的な発展の過程などはあろうが、この時代に「人間」を論ずる際に「他者との関係に生きる、人格的な存在」という理解がなくなっている。その中で我々は「神に造られた存在」としての「人間の尊厳」を聖書から聴いていかなければならない。また、「他者との関係に生きる」「他者に自由に応答する」という人間の本質を思う際、「神」こそが「他者」の最たる者であるということを忘れてはならない。人間は、神との関係の中で自由に神に応答する「責任」を持っている。我々はそのような理解を聖書から聴かなければならない。「礼拝」は神の言葉を聴いて、喜んで従っていく場である。そこに我々の喜びがある。ただ物理的に自分の身体を「礼拝」の場に持っていくのみならず、そこで聴いた神のみ言葉に「応えていく」ことが、我々の「礼拝」である。
3節には繰り返し「主」という言葉が出てくる。それはかつてイスラエルの民に示された神の名前「ヤーウェ」と同じ言葉である(出エジプト3:14「わたしはある」)。この言葉は「どこかにじっと在る」というニュアンスではなく 「神の行動」「ことを成し遂げようとする様子」を表す語である。岩波訳ではこの語を「わたしは成る」と訳し、マルティン・ブーバーは「わたしはそこにあるであろうとする者である」と訳した。「そこに、のっぴきならない場所にあらわれた」という訳もあるが、いずれも「神が自由にご自身とその事柄をあらわそうとする時にそこに成る」というニュアンスを表現しようとしている。我々はそのような神に依拠している存在であると同時に、そのような神に選ばれた存在である。聖書にはその恵みも告白されている(参照:申命記7:6-8)。それは、人間の側の功績や資格ではなく一方的な神の選びと憐れみによる事柄である。選ばれた民は神を礼拝し、主の慈しみと真実を世界の民が知ることができるように神に仕える使命を負わされる。神に選ばれた者は、神に仕える目的を持つ。それはまことの神を賛美し信仰を告白することである。それが神の民の大切な奉仕である。
詩は「主は恵み深く、慈しみはとこしえに 主の真実は代々に及ぶ」(5節)と閉じられている。「慈しみ」という言葉はホセア書のテーマでもある。そこに表わされているような「愛」に富む神は、罪を犯す者をなお贖い救い出される「真実」と「義」に富む神である。神の「愛」「真実」「義」を賛美し告白し、全世界がそれに応えて生きることができるように祈り仕えることが、「神の民の使命」である。