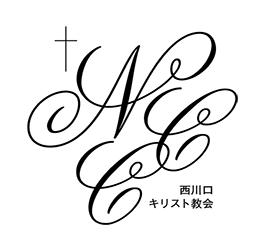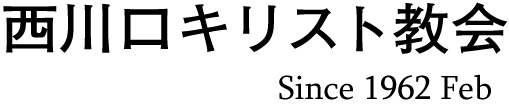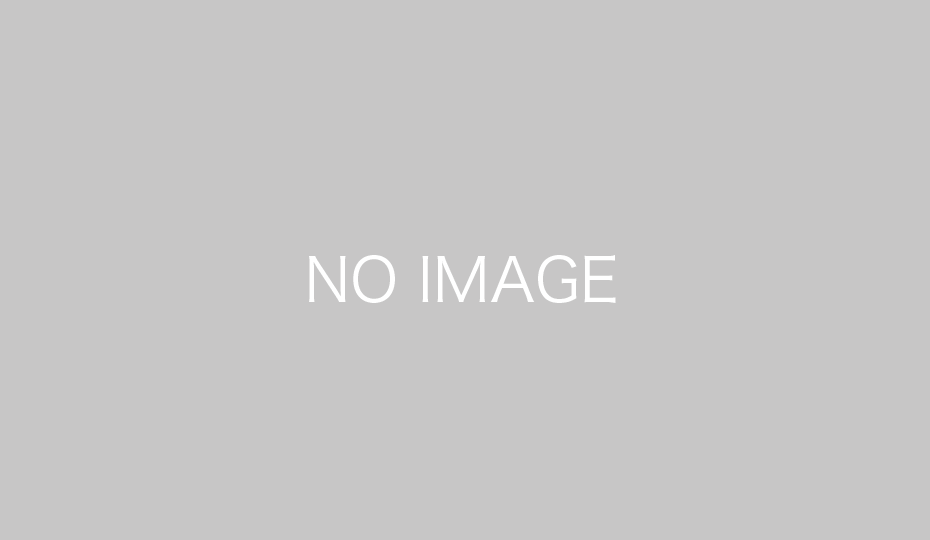「その子アブサロム」(詩3:1)については、『サムエル記下』に詳しい。ダビデは三男アブサロムに反乱を企てられた。その際、今までダビデに仕えていた家臣の多くが息子アブサロムの側に加わり、ダビデを裏切っていく(サム下15:10−12「アブサロムはイスラエルの全部族に密使を送り、角笛の音を合図に、『アブサロムがヘブロンで王となった』と言うように命じた。・・・陰謀が固められてゆき、アブサロムのもとに集まる民は次第に数を増した」)。人々の心もアブサロムに傾いていき(サム下15:1−6「・・・アブサロムは、・・・イスラエルの人々の心を盗み取った」)、とうとうダビデは少数の家来たちと共にエルサレムから逃れ落ち延びていくことになる。この詩は、そのような中で歌われたものである。
ダビデは「主よ、わたしを苦しめるものはどこまで増えるのでしょうか」(詩3:2)と嘆く。自分の息子に反旗を翻されたという事実は、非常にダビデの心を痛めた。また、今まで「自分の家臣だ」と信頼していた者たちに裏切られたのはダビデにとってどれだけ悲しいことであったか。
この詩の直接的な背景となる事件は『サムエル記下』16:5−14に記されている。サウル王家の一族の出身であるシムイという男が、ダビデとその一行に石を投げつけながら呪詛の言葉を投げつけた。「出て行け、出て行け。流血の罪を犯した男、ならず者。サウル家のすべての血を流して王位を奪ったお前に、主は報復なさる。主がお前の息子アブサロムに王位を渡されたのだ。お前は災難を受けている。お前が流血の罪を犯した男だからだ」(サム下16:7−8)。サウルが王位を退きダビデが即位したため、サウルの家系の者にとってはダビデに対して常に何らかの思いがあったことであろう。ダビデが権勢を誇った時期にはダビデに従わざるを得なかったが、ダビデの権力が失墜した今、シムイはこの時とばかりにダビデを呪ったのである。「主は報復なさる」、すなわち「お前の罪に対して神が報いているのだ」というシムイの言葉は、ダビデの耳に痛いものであった。『詩編』に「敵」への報復を願う祈りが多く見られるが、その「敵」とは「神を信じない者」あるいは「自分を陥れようとする者」を指す。自分自身の様々な問題を指摘し、欠点を告発する者であるシムイはまさにダビデの「敵」であった。ダビデはいわゆる聖人君子ではなく、様々な過ちを犯し、弱さをさらけ出して生きた人物である。それゆえに自らの問題や欠点を指摘されたなら、ぐうの音も出ない。権勢を誇っていた時期には何を言われても意に介する必要はないし、そのような指摘をされる場面も少ない。しかしひとたびその権力が傾き始めると、途端に耐えきれないほどの批判と呪いの言葉が浴びせかけられる。
シムイの呪いと告発の言葉を聞き、ダビデの心は穏やかではなかった。しかし、シムイに手をかけようとする家臣に向かい、ダビデは「ほおっておいてくれ。主がダビデを呪えとお命じになったのであの男は呪っているのだろうから」(サム下16:10)と言った。これは教えられるところの多い言葉である。我々は日常生活の中で様々な人から様々なことを言われる。それを思うと夜も眠れないということも少なくない。しかしダビデはここで「ほおっておけ、主がそのように言わせているのだから」と言った。自分を悪く言う者の言葉そのものだけを考えると、非常にやりきれない。しかし自分が「傲慢にならないように」と、神があの人をしてこのように言わせているのだと思えるようになれば、それは幸いである。ダビデにしても最初からそのような境地だったのではない。むしろ「すべての敵の顎を打ち、神に逆らう者の歯を砕いてください」(詩3:8)と祈っている。しかし最終的にはダビデのように「このように非難の言葉を浴びせられていることも、主がくださった訓練」と思えるようになりたい。
「多くの者がわたしに立ち向かい、多くの者がわたしに言います、『彼に神の救いなどあるものか』と」(詩3:2)とダビデは嘆く。「イスラエルの民」という同じ「信仰の民」がダビデに敵し、「お前は神に捨てられたのだ」と言い募るのである。現代日本で生きるキリスト者も、宗教に対して理解のない社会で生きる日々において周囲から様々な言葉を投げつけられる。 自らの信仰やその生き方に関して、面と向かって遠慮のないことを言われることもあるかも知れない。そのような中でキリスト者はどのように対応し生きていくことができるのであろうか。ただ反論したらよいということでもない。どのように忍耐強く信仰を証ししていくのかということが問われている。
2-3節は単なる嘆きではなく、自分が直面している問題を神に素直に告白する「祈り」である。「訴える言葉を発する」という祈りも、とても大切なものである。神は我々の苦境を最もよくご存じではある。主イエスも「祈るときには、異邦人のようにくどくどと述べてはならない。・・・あなたがたの父は、願う前から、あなたがたに必要なものをご存じなのだ」(マタイ6:7−8)と教えて下さった。しかし主イエスは「だから祈らなくてもよいのだ」とはおっしゃるのではなく、まさに祈ることを、「主の祈り」という形で教えてくださった。
ダビデの祈りは訴えだけでは終わらない。「主よ、それでもあなたはわたしの盾、わたしの栄え、わたしの頭を高くあげてくださる方」(詩3:4)とダビデは賛美する。苦しみの中にあっても、「それでも」キリスト者は祈っていく中で主を仰ぎ見ることができる。苦しみの中にあっても「あなたはわたしの盾、身を守ってくださる方」と喜ぶことができる。「頭を高くあげてくださる方」とは、「苦しみの前でうなだれる我がこうべを上げてくださる方」を意味する。辛辣な言葉が投げつけられても防いでくださる方、名誉を回復してくださる方である神に、苦しみの中でも希望をおく祈りがここにある。
「身を横たえて眠り、わたしはまた、目覚めます」(詩3:6)と歌うダビデにせよ、やはり責め立てる者や悪口を言う者のことを思うと眠れない日々が続いたのかも知れない。しかし信仰を取り戻した時、ダビデは眠りを取り戻した。この箇所は「朝の祈り」とも言われる (詩4:9が「夜の祈り」)。
朝目覚め、新しい一日が始まる。しかし敵に包囲されているという事実は変わらない。ダビデは率直に祈った。「敵の攻撃を打ち砕いてください」と我々も正直に願ってよいのである。
しかしダビデの祈りは「救いは主のもとにあります。あなたの祝福があなたの民の上にありますように」(詩3:9)という執り成しの祈りで終わっている。「あなたの民」とはまさに前述の通り、その多くがダビデに敵対しようとしていた「イスラエルの民」である。自分の状況と思いを正直に差し出す祈りは、祈っていく中で「自分に逆らう者にも神の祝福があるように」という祈りへと導かれていくのである。